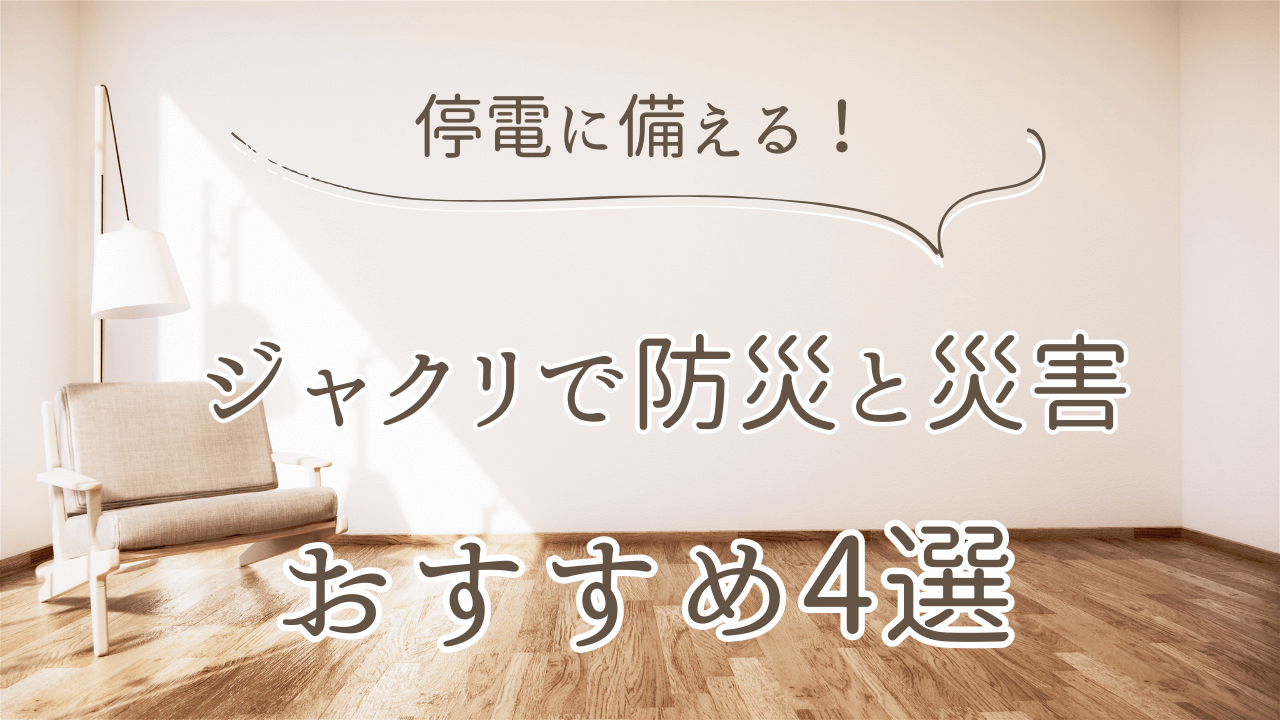停電したら冷凍庫は何時間持つ?12時間以上持つ対策を体験者が紹介

この記事は、停電したら冷凍庫は何時間持つか解説します。
パナソニック公式によると「半日〜丸1日」とありますが、胆振東部地震のブラックアウトを経験した私は「2〜3日は余裕で持つ」と感じましたよ。
食材のまとめ買いをする習慣があり、停電時に食材を捨てたくない方は、12時間持たせる対策をこのまま読み進めてご確認ください。
停電時に冷凍庫は何時間持つのか

一般的に冷凍庫は扉を開けずに閉じたままの状態で庫内がしっかり冷えていれば、停電時に半日から丸一日程度は保冷が可能とされています。
ただし、設置環境や庫内の食品量、季節によって持ち時間は変わるので、ここでは家庭用と業務用の違い、季節ごとの違い、食材による差を解説します。
冷凍庫の保冷時間の目安(家庭用と業務用の違い)
家庭用冷凍庫は容量が小さいため、扉を開けなければ停電時でも通常18〜24時間程度はマイナス温度を保つことができます。
なぜなら、冷凍庫自体がクーラーボックスのように保冷する効果があるからです。
一方で、業務用冷凍庫は容量が大きく断熱性が高いため、停電時でも36時間近く持つケースがあります。
ただし庫内が空に近いと温度が上がりやすく、逆に食品がぎっしり詰まっていれば互いに保冷し合う効果があり長持ちする違いを理解しなければなりません。
夏と冬で持ち時間が変わる理由
冷凍庫の持ち時間は外気温に大きく左右されます。
夏場は周囲の気温が高く、庫内との温度差が大きいため冷気が逃げやすく、保冷時間は短縮される傾向にあります。
一方で、冬は外気温が低いため、庫内の冷気が外に逃げても温度上昇が緩やかになり、比較的長持ちします。
冬場は停電しても24時間近く持つことがありますが、夏は12時間を過ぎると食材の安全性が下がるため注意が必要です。
私が胆振東部地震で数日停電(記憶では1週間近かった)を経験したときは夏でしたが、冷凍庫に食材をパンパンに詰めた状態で、電気が復旧するまで食材は食べられましたよ。
肉・魚・アイスなど食材別に見た持ち時間の違い
肉や魚は冷凍庫内で他の食材と密着している場合は比較的長く保冷でき、12時間程度なら問題ないケースも多いです。
一方で、アイスは温度変化に敏感で数時間でも溶け始めることがあります。
氷は完全に溶けるまで時間がかかりますが、サイズが小さいものは半日程度で形が崩れる場合があります。
停電が長引いたときにやってはいけない行動
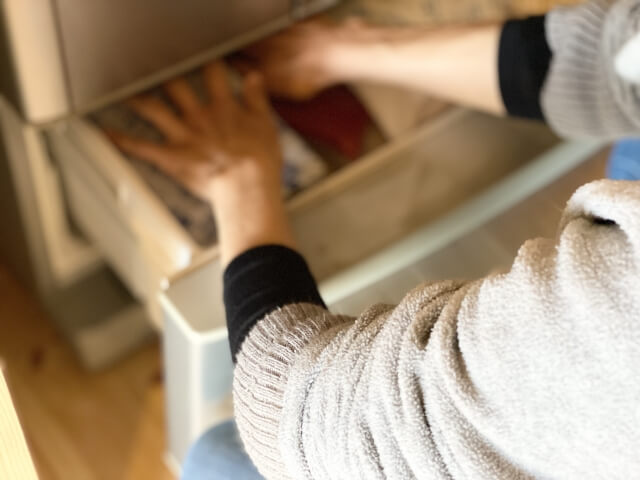
停電が長引くと慌てて誤った行動を取るリスクがあり、冷凍庫内の食材を早く傷めてしまう原因になるので注意が必要です。
ここでは停電時に冷凍庫でやってはいけない、代表的な注意点を3つ紹介します。
頻繁に扉を開け閉めしない
冷凍庫の扉を開けるたびに外気が入り込み、庫内温度が一気に上昇するので、停電時には最もやってはいけない行為です。
夏場は外気温が高く、数秒開けただけでも冷気が逃げやすいため注意してくださいね。
扉を閉じていれば12時間以上持つ冷凍庫でも、何度も開け閉めすると数時間で食材が傷むリスクがあります。
どうしても取り出したいときは、一度に必要なものを決めて短時間で済ませ、無駄な開閉を避けましょう。
クーラーボックスへの移し替えが逆効果になる場合
停電時に冷凍庫の食材を守るためにクーラーボックスへ移そうと考えるかもしれません。
しかし、事前に冷やしていないクーラーボックスは内部が常温に近いため、かえって食材の温度を上げてしまうので避けたほうがいいですね。
また、移し替えの際に冷凍庫の扉を長時間開けることも逆効果になります。
クーラーボックスは十分に氷や保冷剤を入れて冷えている場合に限り有効であり、そうでなければ冷凍庫にそのまま残しておくほうが安全ですよ。
再冷凍で食材を戻すときの注意点
停電が長引いて解凍が始まった食材を、電気復旧後に再冷凍するのは危険なので、止めてくださいね。
肉や魚は一度解凍されると菌が繁殖しやすくなり、再冷凍しても安全性が保証されません。
見た目は凍っていても品質は落ちていることが多く、食中毒の原因になる可能性があります。
再冷凍するか迷ったときは、色や臭いを確認し、不安があれば加熱してすぐに食べるか廃棄する判断を優先してください。
冷凍庫を12時間以上持たせるための具体的な対策

停電が長時間に及ぶと、冷凍庫の保冷力だけでは限界がありますが、工夫次第で12時間以上持たせることは可能ですよ。
ここでは、冷凍庫を12時間以上持たせるための実践的な方法を紹介します。
冷凍庫内に食材をパンパンに詰めて保冷力を高める
冷凍庫は空いているスペースが多いほど温度が上がりやすくなります。
隙間があると冷気が循環しやすいように感じますが、実際には外気の影響を受けやすく保冷時間が短くなります。
そこで有効なのが、冷凍食品やペットボトルを凍らせて庫内をいっぱいにしておく方法です。
凍った食材同士が保冷剤の役割を果たし、互いに温度を下げる効果があります。
私が胆振東部地震のブラックアウトで冷凍庫内の食材を数日持たせられた理由も、冷凍庫に食材がパンパンに詰まっていて、凍った食材が保冷剤の役割を果たしたからでした。
保冷剤・凍らせたペットボトル・ドライアイスを使う
停電時には保冷剤や凍らせたペットボトルを冷凍庫から取り出し、冷蔵室や上段に配置して、冷蔵庫内の食材の鮮度を保つ方法もおすすめですよ。
また、計画停電や事前に停電が予想できる場合には、ドライアイスを準備するといいですね。
4kg程度のドライアイスを冷凍庫の上部に入れておけば、12時間以上庫内温度を低く保つことができます。
ペットボトルや保冷剤は日常からストックできるものなので、我が家では今でも冷凍庫に保冷剤を入れてあります。
発泡スチロールや新聞紙を使った簡易保冷法を紹介
停電中は冷凍庫自体を断熱して温度上昇を抑えることも効果的ですよ。
発泡スチロールの箱で冷凍庫を囲ったり、庫内の隙間を新聞紙で覆ったりすると外気の影響を軽減できます。
新聞紙は手軽に使えるので、庫内の食材の上にかけて温度変化を遅らせるためにも活用してみてくださいね。
停電時に冷凍庫を使う場合の注意点

停電中の冷凍庫は、ただ扉を閉めておくだけではなく、いくつかの注意点を押さえておく必要があります。
ここでは特に注意すべきポイントを紹介します。
溶けた氷や霜による水漏れに注意
長時間の停電で冷凍庫内の氷や霜が溶けると、水漏れが発生します。
この水が床に広がるとカビや傷みの原因になるだけでなく、停電復旧後に漏電のリスクを引き起こす可能性があるので、注意してくださいね。
停電後は冷凍庫の周辺を確認し、濡れている場合は早めに拭き取り、新聞紙やタオルを敷いて対処しましょう。
壊れたと思ったら数分間電源プラグを抜いてみる
停電から復旧した直後に冷凍庫が動かないことがありますが、多くの場合は誤作動や一時的な保護機能によるものです。
その際は慌てて修理を呼ぶのではなく、数分間コンセントから電源プラグを抜いてから再度差し込むと正常に作動するケースがあります。
また、停電中に何度も電源が切り替わるとコンプレッサーに負担がかかるため、自動的に保護装置が働く場合もあります。
まずは落ち着いて再起動を試みてくださいね。
停電でも安心!事前にできる冷凍庫の備えと便利グッズ
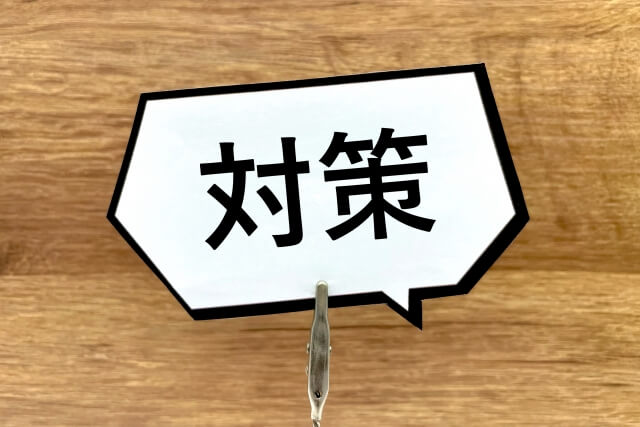
ここでは、突然の停電に慌てないために家庭でできる備えと役立つ便利グッズを紹介します。
冷蔵庫に日常から食材を隙間なく詰めておく
冷凍庫は食材をぎっしりと詰めておくと、相互に冷却し合い、保冷時間を長く維持できますよ。
逆に隙間が多いと温度が上がりやすく、停電時の持続時間が短くなります。
普段から余ったスペースに冷凍できる飲料水やパン、保冷剤を入れておくと、非常時の「保冷ブロック」としても活用できるので、停電への備えとして効果的です。
停電そなえモード付き冷蔵庫など最新機種を使う
近年の冷蔵庫には「停電そなえモード」が搭載されたモデルも登場しています。
これは気象警報などと連動して停電前に予冷を行い、停電が発生した際に保冷時間を延ばす機能です。
従来の冷蔵庫よりも庫内温度を長時間安定させられるため、食材を守る力が向上しています。
これから冷蔵庫や冷凍庫の買い替えを検討するときは、こうした最新機種も検討してみてくださいね。
USP機能付ポータブル電源を繋いでおく
長時間停電に備えるなら、ポータブル電源の活用も効果的ですよ。
UPS(無停電電源装置)機能が付いたタイプなら、停電が発生しても瞬時に冷蔵庫へ電力を供給できるため、冷凍庫を止めることなく運転を継続できます。
容量1,000Wh以上のモデルであれば、家庭用冷凍庫を10時間以上稼働させることも可能ですよ。
ポータブル電源があれば、災害時のスマートフォンの充電や照明にも利用できるため、一台あると安心ですね。
冷凍庫は停電で何時間もつかの情報のまとめ
この記事では、冷凍庫は停電で何時間持つのか解説してきました。
パナソニック公式の情報では、「冷蔵なら2〜3時間」とあり、冷凍庫は「半日〜丸1日持つ」と書かれています。
胆振東部地震のブラックアウトを経験した私の場合は、冷凍庫にパンパンに肉が詰まっている状態で、「2〜3日は余裕」「1週間だと溶け始める」と感じました。
長期間の停電で食材をダメにしたくない方は、できるだけ食材を詰めておく対策や、USP付のポータブル電源の購入も検討してみてくださいね。
SUPやパススルー付きのポータブル電源は、以下の記事でご覧ください。